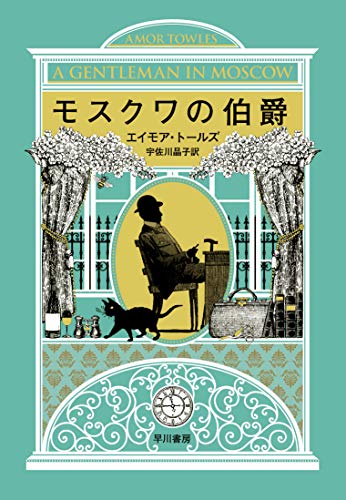濃密な白い闇の中に引きずり込まれたような不快感と疲労感がクセになる カズオ・イシグロ「充たされざる者」
こんにちは。
「遠い山なみの光」、「浮世の作家」で名を上げた彼が、「ブッカー賞」という周囲の期待からも自由になってやっと書いたのがこの作品。文庫本ながら厚さは約5センチ、900ページにも及ぶ超超超大作。手首がつらい…泣
当時は賛否両論あったそうです。まあ正直、私が審査員だったら「ノー!(意味:長い時間をモヤモヤした作品の読解に費やさせやがって)」って言うと思う。笑 ただ、見かけ倒しの駄作だったな…とかいう薄っぺらさ故ではなくて、むしろ逆。情報量も膨大で読むには気力と体力が必要です。世界観はきっちり作り込まれているし、この小説で何を実現したかったもしっかり伝わってくる。実験的小説としての目的は十分に達成されたとみて間違いありません。
…と、優等生的な感想はココまでにして本音を言うと、「上中下巻に分けるべきこのボリュームを1冊にまとめたのは、分けてしまったら中巻以降が全く売れないと踏んだからじゃないの?」って真面目に思っている。それくらい読む人を選ぶし、忍耐力を要求される作品です。少なくとも、「人生を変えた書」にこの本を挙げてみたり、「この本すっごいおもしろかった~」って言う人は絶対信頼しません。笑
主人公はライダーという老ピアニスト。ヨーロッパの小さな都市(おそらく故郷)に招待されて、数十年ぶり?に帰郷します。ライダーが招待された背景は、故郷の「危機」を救うため。世界的に有名なライダーが訪問することで、昔は音楽都市としてちょっとしたものだった街に変化をもたらすことを期待されての招待と思われますが…
と、全部に「おそらく」という言葉をくっつけたほうが良いくらい状況は判然としないし、結局その「危機」が何なのか、ライダーは何者なのか、最後まで読んでもわかりません。
一番最初に会話をしたのは、ポーターのグスタフというおじいさん。娘ゾフィーと孫のボリスについての一連の長話を聞かされた上、娘がふさぎこんでいるから話を聞いてやって欲しいと頼まれたりもする。イライラしながらも依頼を引き受けてゾフィーと話をするライダーでしたが、いつの間にやら、ゾフィーとボリスは妻子ということになっている。
う~ん、ここらへんで嫌な予感がしてくる。
「遠い山なみの光」や「浮世の画家」などの、「事実から目を背け、自分を正当化しようとする人間の勘違いを一つ一つ検証していく系」の小説ではないということがわかる。
カズオ・イシグロの専売特許といえば「信頼できない語り手」ではありますが、妻なんだか息子なんだかもよくわかんなくなっているっていうのは不信感MAX。カズオ・イシグロ作品で堂々のナンバーワンです(自分調べ)。彼はきっと、おなじみの自己正当化に躍起になるオジサンなんかではく、他にもっと重要な役割を持っているオジサンなんだろう、と、開始60ページにして暗雲が立ちこめてきます。
個人的に、カズオ・イシグロ作品の中で苦手とする「私たちが孤児だったころ」「忘れられた巨人」系だとがっくりしたり。笑
普通ならここで解説を読んでみるだろうと思うけど、まぁ、ノーベル文学賞受賞者だし、もう少し頑張ってみようかって自分を奮い立たせて頑張ることにしますが、先に進まない感にイライラしてくる。
特に”不穏な感じ”を受けるのはこういうところ。
時間感覚がない
「木曜日の夕べ」というイベントに参加する予定だっていうことは伝わるんだけど、今日が何曜日か誰も教えてくれません。まだ先のようにも感じられるけど、ホテルの従業員はイベントの準備でずっと出ずっぱりという謎。
また、夜中にホテルに戻ったライダーは、ベッドに倒れ込んでそのまま寝ようとするのですが、迷惑なことに支配人から電話が。「今何してますか??」と平然と聞く支配人。ライダーが「ちょっと寝ようと思っている」と答えると「はぁ、こんな時間に??(半笑い)」というような対応をされ、結局ロビーに降りて行かざるを得なくなるなど。しかも、ロビーに降りるとまだ宵の口だったり…
ライダーは滞在中にたくさんの事をこなしているのに、時間がなかなか進まないんです。昼なのか夜なのか全然わからない上、自分が認識している時間と、周囲の時間が大きくずれている瞬間がたくさんある。大切な用事を、大寝坊して遅刻してしまうような不快感。
慇懃無礼な町の人
ライダー様!!誰もが彼をそう呼びます。
ライダーが町でVIP待遇なのは誰に目にも明らかなのですが、その割に「申し訳ないのですが…」と半分強制的にいろんなことを頼んでくる。予定があるのに他のことに引っ張り回されている間に、ライダーの時間感覚はどんどんゆがんでいきます。
ライダーはいつも疲れ切っているのに、全然寝かせてくれないし。世にも奇妙な物語の世界に迷い込んでしまったような気分になります。
扉を開けるとそこは…
滞在2日目、ライダーがカフェでボリスに甘いものを食べさせていると、これまた慇懃無礼なカメラマンにつかまり、電車に乗ってロケに出かけることになります…読者としては「子どもを一人で置き去りにするなんて!!とハラハラするのですがなんと、仕事を終えてドアを開けるとそこはボリスを置き去りにしたあのカフェだった。イリュージョン!!
こんなことばっかり続きます。ずっと遠くまで連れてこられてきて、そろそろ疲れたから帰ろう…と思ったらそこはホテルのロビーにつながる廊下だった…とか。
ここまでくると、カフカの「城」が嫌でも思い出されます。誰に教わるでもなく、この作品は「城」のオマージュ。超具体性に満ちた細々とした出来事・会話でもって「目的地に到達する」という目的を霞ませて読者を翻弄する様は、カフカの「城」そのものです。昔読んで、「なんじゃこれ」と投げ捨てた記憶のある「城」にこんな形で再会するとは!!
小説を書くにあたっては、登場人物の人格や生まれ育ち、それぞれの信念、舞台、目的…それらを明確にして読者に伝えるのが基本のキしょうが、これに真っ向対立。構想の段階でしっかり作り込んでいるかどうかは置いといて、これらの輪郭を意図的に滲ませたまま、不快感もそのままに1000ページも話を書き続けるその実力たるや!!すごい!
(良い意味で)変態!!!笑
ただ、こういう話は「終わらせ方」が最重要だと思っていて、終わり方については若干不満。この終わり方で良いのかな、っていうのは考え込んでしまいます。少なくとも「これは傑作だったんだ!!!」と太鼓判を押せるほどのすっきり感はなくて…。
身も蓋もない話をすると、「城」は未完だからこそ価値があったのでは…?なんて失礼なことを思ったりもする。
いろんな角度からテーマを見つけて好き放題論じることができそうなこの作品ですが、ジャンルとしてはブラック・ユーモア小説らしいです。
登場人物はみなのっぺらぼうで外見は思い描けませんが、彼らが語る文句はびっくりするほど人間くさくて生々しい。人間世界の面白さ(馬鹿らしさ)を誇張し、象徴的に描いた作品なのかも知れません。
・私は忙しいと言いながらどうでもいい用事を詰め込んでイライラしている
・慇懃無礼な態度で他人の時間を奪う
・本質を忘れ日々の実際的な用事にばかり夢中になるところ
・何か大切なもの(自分の本当の人生)が他にあるはず、と日常のあれこれを雑に扱う
・いつも過去の何かを後悔している
・何かを達成しようとしても、結局うまくいかなくて悲しい
う~ん、刺さる!!笑
充たされざる者(The Unconsoled)とは誰のことなのかな…
話の流れなんてあってないようなものなので、一気に読もうとするのではなく、寝る前に30分ずつ読むくらいがちょうど良いのではないでしょうか。
おわり。
あの銀英伝が帰ってきた!!!「銀河英雄伝説列伝1」
こんにちは。
10月30日発売のこちら、「銀河英雄伝説列伝1」
ずっと前から予約して楽しみにしていました。予想通り数日で読み終わってしまい、再度銀英伝ロスに陥っている今日この頃。2はいつ出るのかな…
「列伝」は、銀英伝を愛する作家が、思い思いに銀英伝の世界で物語を紡ぐという、公式トリビュート・アンソロジー。田中芳樹監修です。
久々に読む銀英伝に、「ああ…ヤン(ラインハルト)が生きている…!!!」とうるうる。また正伝から読み直してみたくなりました。
この本の魅力は、「銀英伝に思い入れがある人向け」に書かれていること。マニア向けと言っても差し支えない。
よく、初めて読む人にも楽しめるようにと、設定や忘れられがちな登場人物をちょくちょく解説してあげるものもあるけれど、こちらはスパルタ系。
アッテンボローにブラウンシュバイク公、アムリッツア会戦に、ナントカ星系…などなど、
わかるわかる~、けど、、、どんなエピソードがあったっけ???
ってなっているうちに置いていかれる。「銀英伝好きなら知っていて当然ですよね??いちいち話の腰を折らないでください」とでも言われてしまいそうな塩対応は、もはや快感。笑
ラインハルトとヒルダの新婚旅行のエピソード。新婚旅行中に予定されていた用事をキャンセルさせて、いきなり「釣りをする!」と言い出したラインハルトには、密かな計画があった…。
エミール・ゼッレを特別な存在として大切に思うラインハルトが、若干(かなり?)空回りしている姿が愛らしい。禿げ上がりそうな激務をこなすラインハルトの休日が、美しい自然の描写と相まってキラキラ輝いているのが素敵だし、その後起こる悲劇を思うと、つい泣きそうに…ラインハルト亡き後の銀河帝国の様子も知れて大満足。
ヤンが士官学校生だった頃に起きた友人の恋物語と、キャゼルヌ妻(当時は彼女)の推理が冴え渡る安楽椅子探偵的なストーリー。
ほっこり感まんさいの恋物語かと思いきや、その裏に隠されたきな臭い事件を「おかしいですね…」とニコニコしながら暴くキャゼルヌ妻。あのキャゼルヌが選んだ妻だから、さぞかし聡明な女性だろう、というところから着想した物語とのこと。
伏線の回収も鮮やかで、謎解きとしての構成も完璧!短編ならではの面白さがある(あと5本くらい同じテイストで読んでみたい)
■「ティエリー・ボナール最後の戦い」 小前亮
待ちに待った艦隊戦です!!!こういうアンソロジーは、ヤンやラインハルトの「オフ」のエピソードばっかりだろうと想定していましたが、ちゃんとこういう艦隊戦があるのは嬉しい。
あるとき、ハカヴィツ星系にある同盟の補給拠点が奇襲された。ハカヴィツ星系は帝国が通常は到達できない場所であるため、同盟は航路情報の漏洩を疑い調査に乗り出す。調査を命じられたペテルセン中将率いる艦隊がハカヴィツ系に到達してすぐ、第二の事件が起こる。この謎の事件、裏ではフェザーンが糸を引いているという、正伝にも出てきそうな超重厚なストーリーです。
死亡フラグをおっ立てまくるティエリー・ボナールの奮戦にハラハラドキドキしてください!
■「レナーテは語る」 太田忠司
推しのオーベルシュタインが登場して嬉しいこちら。オーベルシュタインが情報処理課にいた頃の女性部下とのエピソード(※艶っぽいわけない)
ある女性士官の死をオーベルシュタインとレナーテで追うという、ホームズとワトソンを意識したストーリー。
犬のために元帥が生肉を買いに走る&あの遺言…という、オーベルシュタインの株を上げた?2つのエピソードに絡めているのが最高!!!オーベルシュタインの生き生き?とした姿についついウルっときました。
オーベルシュタインって、正伝でも、最後に全部持って行った感があるよね。
他2作は、個人的にあんまり刺さらなかった感。
「星たちの舞台」
→ヤンを好きな女子ミルズがヤンを演劇(演じる側)に誘うというお話。「ヤンくん!」とヤンを呼ぶ度にくすぐったい…笑
「晴れあがる舞台」
→表題作。正伝にも外伝にも出てこなかった人達(英雄見習い)が新登場。
銀英伝ファンは一気読み必至。とりあえず「事典」を買って「2」までに復習の予定。
「2」がとにかく待ち遠しい…!!
おわり。
モスクワの伯爵
「モスクワの伯爵」
こんにちは。
サマーリーディングリストに入れておきながら、秋の夜長まで積ん読していました「モスクワの伯爵」
「チャーミングな伯爵のステイホーム生活」なんていう触れ込みでしたが、そんなに明るくはなくて、悲しい気持ちになります。やっぱりロシア小説、、、あなどれない。こちらも曇天系小説でした。
1922年のモスクワ。旧体制が崩壊したことで、それまで国を支配してきた貴族らは皆憂き目にあいます。銃殺された者、投獄された者…ストロフ伯爵は、生涯メトロポールのホテルから出てはいけない(出た瞬間に刑が執行される)という処分をくらい、ホテルの屋根裏で暮らすことに。とは言っても、お金は持っているので毎食優雅にレストラン(もしくは部屋食)でとり、好き放題ホテル内を歩き回り、想像したよりも自由に生活しています。
前評判なんかも参照した上で、辛い立場に置かれた伯爵が、なんとか気を確かに持ち、自分も周囲も幸せにしていく小説…というのを期待していました。数人のホテルマンとメイドとお友達的な存在と絆を深め合う的なまったり小説かと思いきや、冒険もあり、裏切りもあり…。ハラハラドキドキ。なんだかんだ言って、600ページ(!!)があっという間。
軟禁生活1日目。
伯爵は名付け親から得た、こんな教訓を思い出します。
不運は様々な形をとってあらわれる。自分の境遇の主人とならなければ、その人は一生境遇の奴隷となる。
この言葉は、今後の伯爵の生活にずーーーっと影響し続ける超重要な言葉。
今まで読みたかった本を読み、今まで通り人に親切にし、自分の人生を大切にしよう。彼はそんなことを決意するのです。
ストロフ氏は伯爵ということで、とてももてなし上手。ホテルマンやメイドは、変わらず伯爵を愛し続けます。王女さまに憧れる少女ニーナと仲良くなり、ともに下々の世界も知り始めます。
余談ですがニーナは、ホテルのいろんなところの鍵を持っていて、どこの部屋にも入り放題の謎少女。ホテルの裏側へ伯爵を連れ出しては、下働きの人の苦労にしつこく言及するあたり、もはや、伯爵にしか見えない妖精かなんかに見えてくる。笑 ここら辺はクリスマス・キャロルを意識しているんだと思うけど…
不便ではあるものの彼の生活はまあまあ許容できる感じで進んでいきますが、もちろんずっとそういう訳にはいかず、新体制の影響や戦争の影などで周囲は変わっていきます。
レストランで冷遇されたり、自分が透明人間のような気がしてきたり…そんな中ある女優と出会うのですが、彼女とのデート(ワンナイトラブ)は最悪の思い出に。
平民出の旧友は、伯爵の立ち位置を軽く飛び越え、今や時代の寵児。予定をドタキャンされたりもします。若い頃は自分が圧倒的優位に立っていたのに…もちろん伯爵は、良いところの出ということもあり、妬んだり、他人の不幸を願う気持ちはあまり持ち合わせていません。ただ、時々自らのそういう気持ちに気づいてしまい、尚更しょぼーん。
こうやって伯爵は、心が折れそうになる中「自分は変わらない」という決意を日々新たにしますが、変わっていく世界についていけません。それならばと自分も変わっていこうと思っても、ホテルから一歩も出られないんだから変われるわけもなく…。
いっそ他の国に追放したらどうか。新天地ならば新たな人生を始めることができようものの、それもできない…これは、新たな人生をはじめさせないという「罰」なんだろう。
なんてことを思う伯爵はやるせない気持ちでいっぱいになります。
悲しい時には悲しい過去が思い出されるのは人の性で、愛しの妹の身に起こった悲劇を思い返しては涙に暮れます。
ここで、200ページくらいのほっこり小説であれば、「それでも変わらない伯爵と、周りの人の絆」というところに着地させるのでしょうが、もちろんそんなわけはなく、600ページ分の葛藤や悲しみ、そしてささやかな喜びも見せてくれるのがこの本の魅力。
人は簡単に流されるし、恩は忘れても仇は忘れない…メトロポールのホテルという「定点」から、人を観察する面白み(哀しみ?)が8割、そして、混乱に紛れてなんとか今の状況を変えようとするとする冒険要素が2割。
良い意味でとても「現実的」な小説です。聖人君子みたいな奴が出てくることもなく、説教臭い奴もいない。それでも時々、ぱっと雲の切れ目から光が注ぐようなラッキーが訪れる。
切ない状況に置かれると、必ずといっていいほど、ドラマのようなどんでん返しを期待しがちですが、そういう状況は皆無で、誰も彼も、自分のことで手一杯。そんな簡単に倍返しできたら苦労しないわけで。自分を変えようと思ったら、部屋でじっとしているだけではなく賭けに出なければならないこともあるし、諦めるべき事もたくさん出てくる。
もちろん伯爵ですから、手にしているものは私たち平民よりも豊かで上質。だからといって、今まで手にしていたものを失う辛さは私たちと変わらない。「特権階級が私たちの地位まで降りてきただけだ」と言えば確かに小気味良い感じはしますが、一人の人間の悲しみにこうもスポットライトを当てられてしまっては、そうも言えなくて…特に先祖代々からの調度品を手放すシーンと、最期まで貴族であろうとした叔母のシーンは悲しくなりました。
微妙な状況に置かれながらも正気を保とうとする伯爵の後ろ姿にエールを送りたくなる。
ステイホームの参考にはならないと思いますが、自分の気持ちを一から立て直したい時には大いに勇気づけられると思います。
おわり。
忘れられたいと思う事柄ほど忘れてもらえず、覚えていてほしい人には覚えていてもらえない ジョゼ・エドゥバルド・アグアルーザ「忘却についての一般論」
こんにちは。
9月発売の白水エクス・リブリス。
「忘却についての一般論」
一見すると哲学論か?と思われますが、れっきとした小説です。
原題は”Teoria Geral do Esquecimento”で、何語かはわかりませんが、
Teoria=Theory、Geral=General
と容易に推測され、Esquecimentoは「忘却」であろうとアタリがつく。
直訳のようですが、どうしてこういうタイトルなのかなぁと思いつつ読み進めていくと、最後になってやっと「そういうことか!!」って目からうろこ。
一読目は叙情的な物語を楽しみ、再読の時に「忘却についての一般論とは?」という目線で読むと、全く別な物語が浮かび上がってきます。
アフリカの一国であるアンゴラが舞台の物語。アンゴラは、1950年代からの独立運動の末、1975年にポルトガルから独立を宣言。その後内戦状態が続き、1990年代になって終止符が打たれた国です。
主人公はルドヴィカという少女で、1975年頃に姉とその夫に伴われて、首都ルアンダにある高層マンション「羨望館」で暮らし始めます。ひどく内向的な彼女は、姉と義兄が消えた後、羨望館から一歩も出ることなく、30年もの月日を過ごします。
30年!?と裏声になってしまいそうな年月ですが、彼女は玄関を封鎖して立てこもり、蔵書を少しずつ燃やして暖をとり、保存用の食料を細々と食べながらなんとか生き抜きます。その間、時代の証人である羨望館は、戦火を逃れる人が去って空き家だらけになり→アウトローな人が不法に占拠し→内戦が集結した後は取り壊しを待つだけになりました。工事のための足場を利用して空き巣に入った少年サバルに発見された時、彼女はすでに、ほとんど目が見えなくなっていました。
なぜ彼女は外に出ることを拒否したのか?一人籠城した30年間…世間から忘れ去られて生きた30年間、彼女は何かを得たのか、それとも失ったのか。忘れられることを望んだ人間、忘れられることを拒否した人間…羨望館の外で暮らす人々の生き様と対比し、「人から忘れられることとはどういうことか」を考えさせる物語。
300ページに満たない中に37もの物語があります。短編とも呼べない、2・3ページほどの覚え書きのようなものが続くので、最初は感動もなく、ぶつ切りのストーリーを追っていく感じになるります。主人公もルドに限らないため、正直、「もっとひとつの物語に入りこませて!!!」ってなるんだけど、いろんな人の物語を多彩な角度から検証するのは、味わい深くもある。
ルドの娘が登場したり、失踪事件が専門の探偵が主役のハードボイルド調の章もあり、ユーモアのセンスは抜群。途中、人間が土の中に消えたという謎の話が出てきて、都市伝説か!?と思ったらちゃんと血なまぐさい種明かしがあったりして、この話は面白かった。ただ、著者は意図して、ユーモアを盛り込んだり、明るい話を書いたのかもしれないけど、私が読んだ印象としては、全体的に「暗っっ!!」という感じ。空元気というか、読めば読むほど切なくなってくるんですよね、何故か。
さて、著者が書きたかった「忘却についての一般論」とは何なのか。
ルドが家にこもってしまった理由は、ある犯罪のせいでした。それ以来外に出歩くのが怖くなった彼女は、閉じこもりがちになり、数十年の時を無駄にしたのです。内戦によって全市民が缶詰状態だった頃は、皆同じ状況でしたから、彼女としても何か楽しそうな雰囲気はありました。しかしその後、外出できるようになってからも、家から出ず、誰とも関わらない人生を選んだ彼女。
老いて後、サバルという少年に出会って、人との触れあいを取り戻した彼女は、「少女だった自分を、傷ついたままどこかの四つ辻に置いてきた」行為、つまり、過去を強引に忘れ去ろうとつとめてきた自分の行いを深く悔いました。時間はかかったかもしれないが、それを乗り越えて世界に飛び出さなかった自分は愚かで、不幸な人間だ、と。
これらからは、「人の愛がなければ人間は生きていけない」「人に愛されるということは、相手の心に深く刻まれること=忘却の真逆」「過去の自分を忘れようとする行為は悲しい行為」…なんていう教訓が得られるんですが、本当にコレは文字通りの「一般論」で、そんなこと他人から言われるまでもねぇよってなったのは私。私からすると、外にいたら男に襲われて妊娠し、家族から一族の恥扱いされた時点で世界を憎んで当たり前では?と思ってしまう。そんなの乗り越えろっていうほうがハタ迷惑な話で。
神は人々の魂を天秤にかける。片方の皿には魂を載せ、もう片方の皿には、流された涙を載せるのだ。泣く者が誰もいなければ、その魂は下に落ちて地獄へ向かう。涙と悲嘆が十分にあれば、その涙は天国へ…
これ読んだ時は「ほおぉ…」と感動しかけたものですが、ルドはこう続けます。
「いなくなって寂しいと思われる人が天国に行くの。…(中略)…そんなはずはないと思う。こんな単純な話をそっくり信じられたらいいなと思うのだけどね。私は信仰心に欠けているのよ」
また、ルドは「神を信じるには人間への信頼が不可欠(人間を信じない私は神も信じない)」とも言っていて、こちらも、「忘却」について語るには欠かせない定理です。人の善良さを信じることができないうちは、存在は無に等しく、忘却されるまでもない存在である。善き人に出会って初めて人は、忘れられることを恐れるようになる、と。
人は直接関わった人の記憶に残ることで、生きた痕跡を残します。世界と交渉を経っている状態では、すでにいないものも同じ。自分という存在を少しでも大切に思うのならば、人と関わる以外にない、そういうことかもしれません。
とまぁ、「忘却について~」ということに一応の結論を出すならこんな感じですが、堅苦しく考えず面白く読んでほしいです。
小説には、とにかく自分の痕跡を消したがる悪の親玉みたいなのが出てくるのですが、彼の思想が「忘却についての一般論」に何らかの示唆をしているように思わせて、別にそういうこともなくて。笑
妻と結婚記念の旅行に出て、「みんなが俺のことを知らないように思える!!」とHAPPYな気分になったり。悪いやつですが、人間臭くて魅力的なキャラではあります。
私と同じく、アンゴラ作家が初めての方はたくさんいるはず。
2013年度フェルナンド・ナモーラ文芸賞、2017年度国際ダブリン文学賞と、高い評価を得ているようです。装丁も素敵なので是非。
おわり。
驚くべき完成度、魅力的な登場人物…もし自分が小説家なら、こんな小説を書いてみたい!エリフ・シャハク「レイラの最後の10分38秒」(早川書房)
こんにちは。
9月発売のこちら。
エリフ・シャハク「レイラ最後の10分18秒」
読み終わった瞬間、「完璧だ!!!」と声が出てしまった完成度。予想以上に素晴らしかったです。彼女、「トルコで最も読まれている女性作家」だとか。
2018年のブッカー賞最終候補だそうです。本屋で目が合って、一目惚れして購入しました。本屋歩きで収穫あると嬉しくなりますよね。
今から30年前のイスタンブール。一人の娼婦レイラが息絶えました。完全な死に向かうまでの10分38秒間、彼女は辛い生い立ち、イスタンブールへ逃げたときのこと、そして、イスタンブールで得た貴重な友のことを想います。
レイラの思い出と5人それぞれのエピソードが、ゆるやかに混ざり合いぶつかり合い、激流に飲み込まれたり…まるで川の流れのように連綿と続きます。
…と、叙情的な前半部に対して、後半はハラハラドキドキの展開。
親族が遺体の引き取りを拒否したせいで、身寄りのない者の墓に葬られてしまうレイラでしたが、5人の親友たちは黙ってはいなかった!!レイラを「本来あるべき場所」に葬るため、なんと深夜の墓暴きに挑戦する彼らの、どこか悲しい一夜の冒険が描かれます。
イスタンブール…それは不満を抱えた者や夢を追う者がみな行き着く町。治安も悪く事件ばかりのこの町で、望まない生を生きる彼らから、ちょっとだけ勇気を分けてもらう、そんな小説でした。
この本の一番の魅力は、宗教とは愛とは友情とは家族とは…こんな漠然としたテーマを率直な言葉で真摯に語り尽くしてくれる点、そして、著者のメッセージが登場人物の意識や言動に練り込まれ、まったく浮いていない点です。
雑な小説の中には、登場人物の生まれ育ち・性格などを作り込むことを放棄するばかりか、全員にとりあえず暗い過去を持たせて「そういう悲しい過去を持っている人同士にしかわかり合えない世界もあるよね」と、悲しみを持つ彼らをを十把一絡げにして、別の世界の住人としてうちやってしまうものも多いと感じます。そしてその中に出てくる「かわいそうな過去を持つ人」は、根は優しく仲間思いで、その過去の出来事ゆえに予測のつかない行動をとりがちだが、びっくりするほど欲がなく、一度信じられる仲間を見つけたが最後、世界全員に対して優しくなれると相場が決まっている。
私の見る限り、彼らは善人でなければならず、”その悲しい過去ゆえ”に誰かを傷つけることは許されますが、いったん”改心”したあとは、アレは嫌コレも嫌とわがままを言うことすら許されない雰囲気すらある。それは、「かわいそうな過去がある人は善き人でないとフォローしきらん」という無言のプレッシャーにも思えてきます。
この小説に出てくるのは、上記に出てくる天使のような登場人物とは違い、かわいそうな過去やコンプレックスを持っていながらも、人並み以上に欲深かったり、「わたしは嫌です!」と断れる強さを持っている生々しい人間ばかりです。だからこそ、「断じて共感できねぇ!」と思うようなことを平気で言っちゃうし、「貴重な親友なんだから、もう少し相手の気持ちに配慮しろや」とたしなめたくなるようなシーンもある。
「切ない過去を持つ人たちが大都会のはじっこで身を寄せ合って頑張る姿」を心のどこかで期待している読者に対し、容赦も忖度もしない生身の人間ぶつかり合いが本当に魅力的だし、彼らの背負っているものをじっくり考え、言い分を素直に聞いてみようと思えるのです。
例えば全く違う宗教観。「心の救いである」という人もいれば、「私はこれをしますから、救ってくださいという交換条件の取引としか思えない」という人もいる。「いろんな罰は考えつくくせに、いざ人間に必要とされたときには人間をろくに守りもしない」と痛烈に批判する人もいれば、「信者という家族を得たと言われたが、結局心の平静は得られなかった」と答える人がいます。もちろん言い合いになったりする。
「心の救い」と言った女性は、父と母に愛されて育ってきた女性。「取引」と言った女性は同性愛が露見して故郷を追われ、「いろんな罰は考えつくくせに」といったレイラは、父の弟からの性暴力を家族全員からなかったことにされた過去を持つ。「信者という家族に安らぎはなかった」と言った女性は、自己の改宗によって家族から追い出され、イスタンブールへ流れてきました。それぞれの意見を吟味し、彼らの背景に思いを馳せてやっと、「家族に恵まれたか」というただ一点が、彼らのその後の人生に大きく影響しているのでは、と思い至ります。
このように、心にとどめておきたい一言がたくさん出てくるばかりか、それらが生まれ育ちや、彼らが身につけてきた価値観としっかりリンクし、違和感なく理解できる。それはひとえに、登場人物一人一人に、文字通り命が吹き込まれているからなのでしょう。本当に魅力的な登場人物たち…!!
そんな登場人物の魅力は他にもあります。それは、せっっかくできた5人の親友と、傷のなめ合いなんてする気のないパワフルな姿です。彼ら、互いへの無理解が原因のトラブルをしょっちゅう起こしています。間違っても、「私たち、悲しい過去を持っているから100パーセントわかり合えるナカマ!!」なんてことはない。
「家族は大切」という無意識のコメントに傷ついた女性が「血族と水族。良い家族を持ったならラッキーで済ませればいいじゃない。そうじゃない場合だってあるんだ」と悲しみに浸るシーンだってあるし、相手の壮絶な過去を知っていながらもなお、「自分の人生を修復する過程で誰かを傷つけてはいけない(から、今からでも相手に謝ってこい)」と諭すシーンもある。
そんな彼らからは「他人の幸不幸を勝手に推し量るな!」というメッセージが読み取れます。同じように辛い過去を持っている親友たちであっても、自分の幸不幸については口を出させない。そんなことされたら、ぶち切れて取っ組み合いさえしそう。
世の中には時々、勝手に他人の人生を「それでも幸せそうだよね」と点数つけてくるやつがいます。ともすればレイラのこんな人生を「複雑な家に生まれ、家族に疎まれたけどイスタンブールに出てきて5人の友を得た。最後は殺されちゃったけど、それでも彼女の人生は総合的に見て幸せだった」なんて評価しようとする人さえいる。でも決して、そんなことはない。レイラは最後「どこで自分の人生を間違えてしまったのだろう」と自問しながら死んでいったのだから。
ある程度の年齢になると、世界は公平でないということに気づくし、皆が皆幸せになることはできないということにも気づき始めます。自分の人生「ハズレ」だったかもしれない…そんなこと自分が一番わかっているのに、「でも君は幸せだよ!!」なんて言われたくないし、絶対言わせない。たとえ親友であっても。
心に大きな「不可侵の領域」を持つ彼らが、自分の気持ちに折り合いをつけながら、それでも助け合って生きていく、そんな関係性が本当に素晴らしい。著者はきっと、友人に恵まれていることでしょう。
とにかく著者の視線が優しくて、思いやりに満ち、何度も泣きそうになりました。
自分が小説家だったら、いつかこんな小説を書いてみたい!そんなことを思います。
今年のベスト10間違いなしのこの小説を押しのけて、ブッカー賞を受賞した「誓願」は今月(10月)発売!それも合わせて楽しみです。
おわり。
ラーラ・プレスコット「あの本は読まれているか」
こんにちは。
ラーラ・プレスコット「あの本は読まれているか」
2020年3月発売。
書物が人の意識を変え、ついには世界を変える!そういう夢のようなコンセプトの「ドクトル・ジバゴ」作戦を成功に導いたCIAスパイのお話。ただ、出てくるのは「堅実なスパイ」そのもので、疾走感もなければ緊急事態もない、穏やかなスパイ小説。いかにも!というスパイ小説を期待した人はちょっとがっかりするかもしれませんが、すごく面白かった!
この本、主人公は人間ではなく、「ドクトル・ジバゴ」という本そのものかもしれません。
というのも、「ドクトル・ジバゴ」作戦を遂行するアメリカのCIAスパイ女性、対して「ドクトル・ジバゴ」をめぐって辛い経験をした著者のボリスとその愛人オリガ。一言も言葉を発さない「ドクトル・ジバゴ」だけがその中心にあって、皆の悩みの種になったり希望になったりするのですから。
そんな読書家の夢とも呼べるこの本、なんと!実在の「ドクトル・ジバゴ」作戦を綿密に取材し、足りない部分を想像力で補って完成させたという、実際にあった話をモチーフにしているというから驚き。「ドクトル・ジバゴ」ももちろん実在します。(映画のほうが有名らしい)
西:
CIAのソ連部に新たにタイピストとして採用されたイリーナは、スパイとしての才能を買われスパイの訓練を受けることになります。事情を知っているサリー、テディ、ヘンリーなどと、初めて居場所を持ち、充実した生活を送っていたイリーナはついに、「ドクトル・ジバゴ」作戦の重要任務を果たします。しかし、サリーの失踪と秘密の露見により、居場所のない生活に逆戻り…
東:
有害本である「ドクトル・ジバゴ」を書いたボリスとの不倫関係のせいで、矯正収容所(思想犯とその関連者を収容して矯正する場所)に入れられたオリガ。釈放後は母親も子どもも捨ててボリスのもとに戻りますが、収容所暮らしの傷は癒えず、ボリスへの不信感も募ります。自分をごまかし続けていますが、スターリンの死を機に、ボリスが「ドクトル・ジバゴ」の出版にまたもこだわり始めるのを目にし、強制収容の日も近いと怯える日々…
と、幸薄っ!と突っ込みたくなるような2人の女性が中心人物で、幸多かれと応援したくなる。ズバリ!というテーマもなく、あえて言えば「女の生きづらさ」が随所にちりばめられた、かなりノンフィクションに近いフィクション。ノンフィクションやドキュメンタリーは、自分が思うような結末を迎えないのは世の常ですが、これもそんな感じ。ああ、そういうところに落ち着くか、、、となる。悪いやつはのうのうと生き残るし、良い人間ばかりが割を食う。
「ドクトル・ジバゴ」は、一見恋愛小説なのですが、ソ連では禁書扱いになっていました。「動物農場」と同じ、反体制的な作品だったからです。それに目をつけたのがアメリカで。これを密かにソ連に広めて、アナタの国ではこーーーんなに情報統制・言論統制されてるんですよ、と、民衆に知らせることで、すごい遠回りではありますが、東側の弱体化を狙っていました。
スターリンの死後、ボリス・オリガはソ連での出版を目指そうと様々な出版社に原稿を持ち込みますが、出版社は及び腰…。諦めようと思っていた矢先に、イタリアの出版社がボリスに出版を持ちかけ、イタリア語訳して出版してしまいます。
CIAでは、手っ取り早く、イタリア語→ロシア語訳でソ連に広める案もありましたが、イタリア語を介しては原文の魅力が失われてしまう(Google翻訳も、日→英→日ってやるとすごいことになるし)と考え、ボリス直筆原稿の入手を決意。ついに万博の日、ドクトル・ジバゴを秘密裏にばらまくことに成功します。
この小説で目立つのは、働く女性の不遇に対する風刺。西側では、「同じ大学を出ているのに給料が下」、「女性はタイピストしての仕事しかない」、「成果を全部男に持って行かれる」「女はちょっとのミスで追放されるが、男は様々なチャンスを与えられる」などなど。今はアメリカは相当改善されているのだとは思うけど、「女性は減点法で評価され、男性は加点法で評価される」というのは、日本では未だ現存している価値観だと思います。
個人的に、日本のそういう政策は、この前見た「プラダを着た悪魔」と同じ時代に追いついているかどうか、くらいだと思うんだけど、「女は家庭生活のことで批判されるけど、、男は仕事ができればそれだけで賞賛される…」ってアン・ハサウェイが言ってたし、今の日本は、やっとここら辺の違和感が可視化されてきたくらいだよな~、ってなる。
ただ、MAX期間の育休と10年以上の時短勤務で、出世を完全に諦めモードの事務職女性が最も生き生きしている(自分調べ)であるのと同じように、この小説に出てくるタイピスト達があまり悲観しないところが魅力。噂話に興じ、ランチはおいしい店を渡り歩き、いやな男がいたら全力でグチを言い合う。
タイピストの話に始まり、タイピストの話で終わるこの小説は、イリーナでもサリーでもない、スパイ活動を(なんとなく感じていながらも)遠巻きに眺めていたCIAタイピストが、歴史の中で存在を消されてしまうスパイ女性の物語を、記憶にとどめておこうとする構成になっていて、好き。イリーナやサリーを、男性優位社会と共闘する同士と捉えているタイピスト達が、いたわりの心を持って彼女たちに接しているシーンにじーんとします。
「スパイ小説とは違う」と最初に書いたものの、スパイ活動は生き生きと、魅力的に書かれます。例えば万博の時の本の配布。修道女に変装したイリーナらが万博会場に集います。秘密の符牒、最小限の作戦会議、お互いに何者かも知らないながらも連携の取れた行動…。あとは、クリーニング屋を介して書類をやりとりするとか、ベンチに置き忘れた風にやりとりするとか。
個人的に一番好きだったのは、バレないように、既存の本の表紙をくっつけたらどうか?と意見が出て、古典的傑作を偽装した「ドクトル・ジバゴ」が大量に作られるところと、二重スパイが密告によって当局に捕まったときの、「(ホテルの)ボーイ2名が彼の部屋を訪れ、何分か後にボーイ2人は荷物を1つもって出ました」みたいな表現。
「ペンは剣より強し」を地で行くような小説。文学が人に与える影響を信じ、いい大人(しかも選りすぐりのエリート)が必死に「ドクトル・ジバゴ」を取り合う様はおかしくもある。この本は、膨大な資料をもとに(2014年に「ドクトル・ジバゴ」作戦の機密文書が公開)空白部分を自分の想像力で埋める中で、生きているうちに得られた違和感も反映して一つの物語に仕立てただろうなぁ…と推察されます。
いくらでも面白い展開に作り上げられそうな事件をあえて見逃し、あくまでも事実に基づくフィクションであることにこだわった著者、結構実力あるのでは??次回以降の作品も自ずと期待されます。
ちなみに著者の名前はラーラ。「ドクトル・ジバゴ」の主人公ラーラからとられている、という嘘のような本当の話。彼女にとっては相当思い入れがあったことでしょう。
おわり。
ジョン・クラカワー「空へ」
こんにちは。
ジョン・クラカワー「空へ」
数年前に「エベレスト」という、1996年にエベレストで起きた大量遭難事件について取り上げた映画がありました。当時映画館でも見て、映像の美しさ、極限状態での人間ドラマに圧倒された記憶があります。極寒の登頂付近で「暑い・・・」といいながら服を脱ぐ男性の姿に衝撃を受け、ずっと忘れられない作品となりました。
今はアマゾンプライムで!!無料で!!見ることができます。読み終わってすぐ再視聴しました。
さて、かたやジョン・クラカワー。
「荒野へ」、「信仰が人を殺すとき」ですっかり魅了されてしまった私は、過去の著作をあたっていたところ、1996年のエベレスト大量遭難事件のドキュメンタリーを発見。映画でも見たこの話、さぞやすごい内容だろうと思って購入したらなんと!!この事件の当事者であることが発覚し、二重に驚き。この本は彼の名を世に知らしめた出世作です。
1996年、エベレストの商業登山は社会問題になりつつありました。商業登山とは、ろくに登山具も使えない登山者であっても、760万円(当時の金額)を支払えば、エベレストの山頂を目指せるというもの。自分の身一つあれば、ガイドが山頂まで同行してくれる。そして、ルート工作、酸素などの運搬、食事の世話など、身の回りの面倒ごとはすべて高山帯で暮らすシェルパに丸投げできるというもの。お金次第ではエスプレッソマシンまで持ち込める!!
物語の主人公は、エベレストの商業登山にいち早く取り組み、確固たる地位を築きつつある「アドベンチャー・コンサルタンツ社」のロブ・ホール隊「マウンテン・マッドネス社」のスコット・フィッシャー隊。ロブ・ホールとスコット・フィッシャーはライバル関係にありますが、相手のことは信頼しています。
ロブ・ホールは顧客に対して手厚いガイドを売りにしており、その分費用も高額。対してスコット・フィッシャーは、社名からもわかる通り放置主義。実力のないやつは山に登るな、とも思っています。ジョン・クラカワーは商業登山について取材するためにロブ・ホール隊の一員として山頂を目指します。
映画で得た印象は、冬山登山ってチョー危ない、危険すぎる、ちょっとミスればすぐ死ぬ、っていうものでしたが、本を読んで思ったのは実は逆。2つのことを守れば、生きて帰ることは、そこまで難しくない、というもの(もちろん落石・雪崩などに巻き込まれ…という事故は除く)。
一つ目の約束とは、相当な対策。これは、日々のトレーニングに始まり、豊富な登山経験、ルート工作、十分な酸素と荷物…などなど。
二つ目の約束とは、内なる声に従うこと。具体的に言うと「危険を感じたら戻ること」もしくは「決められた時間に引き返すこと」。肝心なのは無事に降りてくることです。登って終わりではない。自分の実力をしっかり見極めて「これ以上は無理」と思ったら潔く下山する
この2つを守ることにより、無事に帰還する確率はぐんと高まるのです。
とはいうものの、営業登山では1つめも2つめも金で解決可能。必要な物資も、経験に基づく内なる声も、ガイドとシェルパ頼みで補える。山を聖地と考え、登頂に至る過程を重要視する昔ながらの登山者から見ると、これは人間の思い上がり以外の何物でもなく、だからこそ営業遠征隊は問題視されていたのです。しかし、ネパール政府は対策をとらないばかりか、入山料の値上げにより外貨を獲得しようとさえしていました。
エベレスト大量遭難事件は、本当にたっっくさんの人でひしめくエベレストで、数え切れないほどの判断ミスが重なって起きてしまった事件でした。事件そのものについてはwikipediaでも臨場感ある内容を得られるので割愛しますが、人の多さ、お客さん気分の登山客(自覚不足)、ガイド、顧客ともに登頂への執着が強すぎる…こんな要素が複雑に絡み合って、起こるべきして起きた事故であると感じざるを得ませんでした。
皮肉にも、マズい状況をいち早く察知し「こんな状況では事故が起きてしまう…」とつぶやいたロブ・ホールの予言通りになってしまったのです。
なぜ、人は山に登るか。
「そこに山があるから」以上の言葉を見つけるために、エベレスト登頂に志願したジョン・クラカワーでしたが、商業登山隊のメンバーと過ごす中で違和感を覚えます。話題作りに思えるような動機だったり、記録を残すために登るという人、登ることが夢だったという割には日頃の鍛錬は足りていなさそうな人、クラカワーが最も親しくしたダグ・ハンセンという郵便局員(犠牲者)は、ダブルワークをしてエベレストを目指します。「こんな自分が登ることで子どもたちを勇気づけたい」という思いがある上に、昨年は目と鼻の先で登頂を断念している彼の執着は相当なものでした。
もちろん、気持ちはわかるんだけど、皆「登頂ありき」であり、そこに至る過程や自己の成長にはあんまり興味ナシのメンバーに若干の失望をします。何人かの印象はその後変わることになりましたが。
対して、元々クライミングが大好きなクラカワーは、山=聖域、登山=神聖な行為という意識を少しだけ持ち合わせていました。著書の中で彼は、先人の著書を多々引用していますが、長々と引いたのはこれ。
登山の魅力はいろいろに言われるーー個人と個人の関係を単純化してくれる作用とか、友愛をスムーズな相互作用に還元してくれる作用とか、人との感情的な結びつきを他のものへ転化してくれる作用とか
(中略)
加齢や他人に対する脆弱や、個人間の義理、あらゆる種類の弱さ、遅々として進まない平凡な人生、そういったものを生真面目に受け取ることを拒絶しようとする意思があるのかもしれない…
うーーーん!尊い!!!
他にも、固定ロープと自分を固定して登山する商業登山と、信頼できるパートナーと自分を固定する(命を預け合う)昔ながらの登山を比較し、信頼できる山仲間がいないからこそ商業登山を利用するんだ…としみじみ感じていたりもします。
山に登る理由なんてもんは人それぞれで構わないですが、登頂にこだわりすぎることは命に関わる大問題です。
こんなエピソードが出てきます。実力も実績も十分にある、単独登攀に挑んだ青年は、ロブ・ホールらよりも数日早く山頂アタックし、あと60分登れば登頂というところであっさり引き返してきます。これ以上登れば無事故で下るのは難しいと判断したから、という理由でしたが、この話を聞いたロブ・ホールは、彼の判断を「なかなかできるものではない」と賞賛するのでした。無事に降りるまでが登山、ということですね。
このエピソードといやでも対比されてしまうのが、ロブ・ホール隊、スコット・フィッシャー隊はじめ、営業遠征隊のメンバーの一部です。14:00までに登頂できなかったら引き返す、という決まりを守らず、一番最後の人が頂上を降りたのはなんと16:00近くになってからでした。その後の悪天候で、大量の人が遭難し、命を落とします。山頂付近でどういう会話が交わされたかはわかりませんが、登頂へのこだわりは隊員だけでなく、登頂者数が翌年以降の営業にもろに直結するガイドにだって十分あったのかもしれないとクラカワーは振り返っています。
約1000万円の出費、数週間に渡る休暇、夢、野望…
これだけのものをかけた以上、結果を出すことにこだわるのは想像に難くありませんが、あまりにも多くのものを背負いすぎると、人生ごと山に持っていかれる、そういう意味で山は恐ろしい場所なのです。
「山は身軽で登るべき」
もちろん装備の話ではなく、あれもこれもと山に託すのは相当危険だという印象を受けました。山登りは時に人生に例えられますが、「全力で登ってはいけない」って実は生き方にも通用していたり…なんて思ったり。
商業登山を云々することはできませんが、心のどこかに、山の中くらいでは、人間の命は平等であってほしいという思いはあります。本来は命を預け合うバディと、文字通り一蓮托生で登るべきもの。だけど、そんな山仲間作りから登山ルートまでを他人に丸投げした上、自分の力不足のツケまで、金に物言わせて他人(主にシェルパ)に支払わせるのはどうか…と思ってしまう。
ただ、数週間の登山シーズンに、西洋人を神聖な場所エベレストに登らせるのを手伝うことで暮らしているシェルパがいるのは忘れてはなりません。貧困が根底にある以上、根は大変深い問題です。
息もつかせず2日で読み終えてしまいました。
描写の細かさに圧倒され、エベレスト登山した気分…とまではいかないけど、ベースキャンプに着いたくらいの気分にはなれました。
おわり